子どもが何かを「やりたい!」と言ったとき、それをどこまで尊重するべきか悩むところですよね。
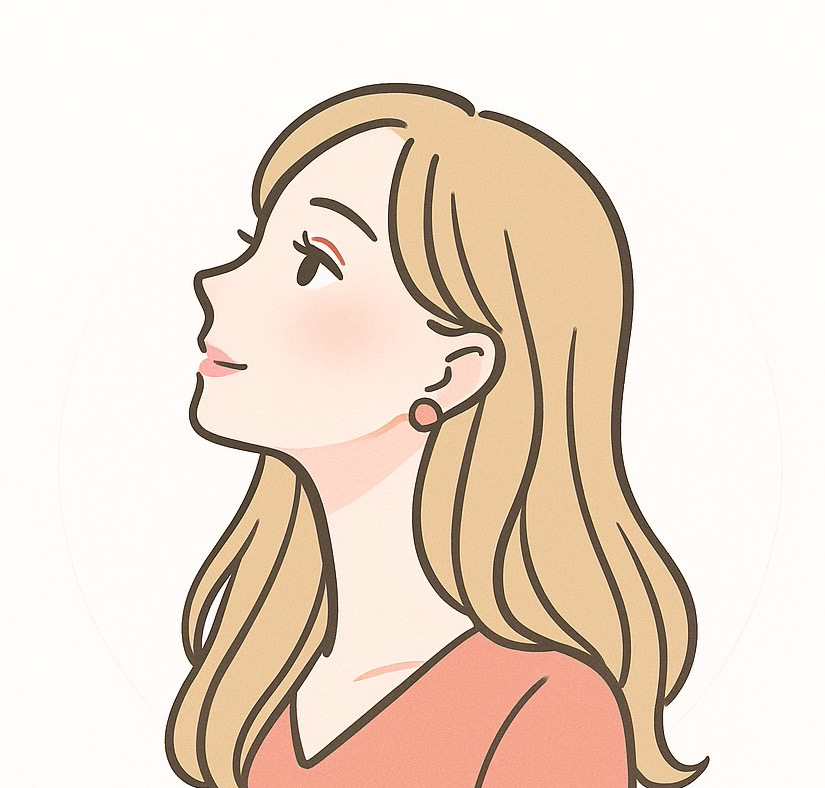
この記事では、子どもの「やりたい!」を尊重することで得られる主な効果と、注意点についてまとめてみました。
子どものやりたいことを尊重すると起こる変化3つ
① 自己肯定感が高まり、挑戦を楽しめるようになる
親が子どものやりたいことを尊重すると、子どもは「自分の気持ちが大切にされている」と安心し、自己肯定感が育ちます。「自分の気持ちが受け入れられた経験」はひとつの成功体験となり、挑戦そのものを楽しむことができるようになります。
親にとっても、子どもの自主性が伸びることで、成長の手応えを一緒に感じられるようになるでしょう。
たとえばこんなとき
- 自分で服を選びたがるとき
- 自分で靴を履きたがるとき
- 自分でスプーンを持ちたがるとき
- お料理など、ママのお手伝いをしたがるとき
② 親子関係が安定し、信頼が築ける
子どもの意志を尊重することは、親子関係の安定につながります。
たとえば習い事を選ぶとき。
親が子どもの意見を尊重すると、子どもは「自分は理解されている」という信頼感や安心感を得られます。するとのちに反抗期を迎えたときでも、困ったことがあると「親に頼ろう。相談しよう」と自然と思うようになるのです。
親子の間に築かれた信頼は、進路の選択や人間関係などにも良い影響を与えてくれます。
③ 線引きを誤ると「我慢ができない子」になる危険がある
子どものやりたいことを尊重する姿勢は大切ですが、それが行き過ぎてしまうと「我慢ができない子」になってしまう危険があります。
すべてを思い通りにさせていると、学校や社会で困難に直面したときに挫折しやすくなり、つらい思いをすることになるでしょう。
子どもの気持ちを尊重する部分と、親が制限する部分とのバランスを取ることが大切です。
たとえばこんなとき
- お菓子を欲しがるとき
- おもちゃを欲しがるとき
- YouTubeを見続けたがるとき
- 夜遅くまで遊びたがるとき
親が子どもをうまく導くためにできること3つ
① 子どもの意思を尊重しつつ、子どもに責任も持たせる
たとえば子どもが自分で選んだ習い事をやめたいと言ってきたとき。
「自分で決めたことだから、一定期間はがんばってみよう」と伝えることで、主体性と責任感を同時に育てられます。(※ただし、教室で意地悪された・先生との相性が明らかに悪い、などは例外です。)
子どもの未熟な判断に親が一定の制限をつけることで、子どもは自分で選んだことに責任を持ち、困難にも前向きに取り組む力を伸ばしていけます。
② 親と子の力関係のバランスを取る
子どもの希望をすべて無条件に受け入れてしまうと、子どもは我慢を学ぶ機会を失い、自己中心的な行動に慣れてしまいます。
反対に「あなたの将来のためだから」と言って親の価値観を強く押し付けてしまうと、子どもの意欲や主体性が奪われます。
親と子の力関係のバランスを取るためには、
- 子どもが親に対してどんな希望でも言えること
- 「希望を叶えるためには親も納得する必要がある」と子どもが理解していること
この2点がとても大切です。
③ 安全面・金銭面・生活面など、各家庭の状況の違いも理解させる
子どもの意思を尊重する際には、判断基準を持つことも大切です。
「安全に通うことができるか」
「無理のない費用で続けられるか」
「家庭や学校生活との両立はできるか」
などを親子で確認し、話し合いの場を持ちましょう。
家庭の基準があることで、親のほうも主観や感情で判断することがなくなり、子どもと対等な立場で話し合うことができます。

今日からできる!尊重とサポートを両立する行動3つ
①「やりたいんだね」と、子どもの気持ちをまず受け止める
子どもが「やりたい」と言ったとき、最初に必要なのは賛否を判断することではなく、その気持ちを受け止める姿勢です。
「これがやりたいの?」
「そうなんだ。じゃあちょっと調べてみようか」
と言葉で返すだけで、子どもは安心して自分の気持ちを表現できるようになります。
受け止めることは許可することとは違います。まず共感を示すことで、親子の信頼関係を深めましょう。
②「どうすればできると思う?」と一緒に考える時間をつくる
やりたい気持ちを受け止めた後は、実現するための方法を一緒に考える時間を持つことが大切です。
「どうすればできるかな?」と問いかけると、子どもは自分で計画を立てたり工夫したりと、現実的な判断力が身につきます。
③ 成果より「過程」をほめ、次につなげる声かけをする
子どもの挑戦を支えるときには、成果だけでなく過程を評価することが大切です。
「自分で考えて工夫したんだねー」
「がんばって最後までやり切ったね」
といった言葉は子どもの努力を肯定し、自信につながります。
また、失敗したときこそ「次はどうすればもっと良くなるかな?」と声をかけることで、挑戦を継続する意欲が育ちます。
さいごに 親の過ちも子どものお手本になる
子育てでは「正しい方法」を探しすぎて、親自身が疲れてしまうことがあります。
しかし、すべてを間違えずに子育てを終える人なんていません。「あのときの判断は間違いだった」と親が認めることで、子どもは「大人も間違えることがあるんだから、自分が間違えるのも普通のことなんだ」と思えるようになります。
親の過ちというのは、子どもに一種の安心感を与えます。間違えたときにはどうしたらいいのかを、親自身が子どもに示すチャンスともいえるでしょう。
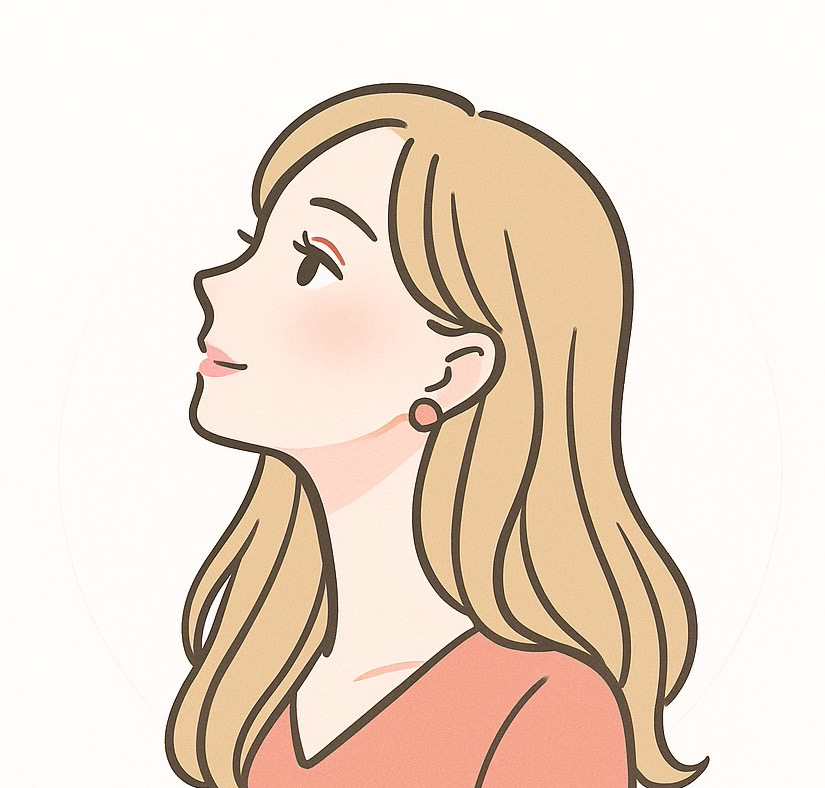
親の心の余裕は子どもの安心感につながります。肩の力を抜いて、これからも育児を楽しんでくださいね。



コメント