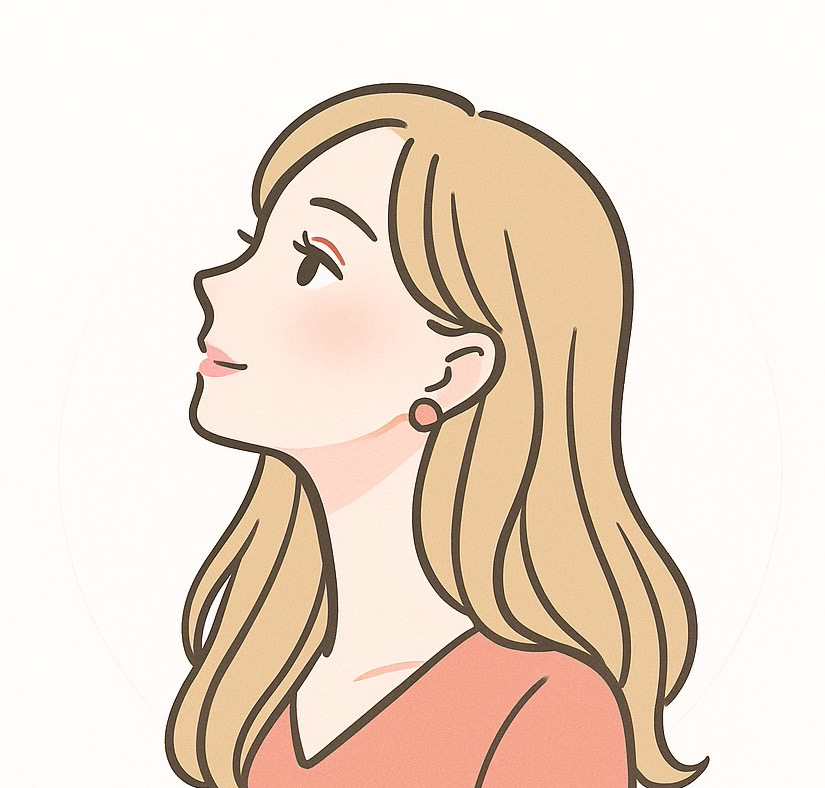
この記事では、子どものやる気を引き出す工夫と、「習い事やめたい」と言われた経験のある親御さんたちの体験談をご紹介します。
子どもが習い事にやる気を見せない原因
興味や関心の変化
始めた当初はワクワクしていても、通っているうちに他のことに興味が移ってしまうことがあります。成長の過程で関心が変わるのは自然なことといえます。
指導者や環境との相性
先生との相性や教室の雰囲気が合わないと、楽しさを感じにくくなります。小学生の場合は特に人間関係の影響を強く受けるため、「好きだった習い事」が苦手なものに変わることもあります。
達成感や成功体験の不足
「できた!」という体験が少ないと、子どもはつまらなく感じやすいものです。練習や学びの成果が見えにくいと、モチベーションを失ってしまいます。
親の期待とのギャップ
「せっかく始めたのだから続けてほしい」という親の期待がプレッシャーとなり、「やらされている」と感じる子も少なくありません。
やる気を引き出すための解決策
小さめの目標を設定する
大きな成果を求めるのではなく、「次のテストで1つ合格を目指そう」など短期的なゴールをつくると達成感を得やすくなります。
ひとつひとつの成功体験の積み重ねが、大きなやる気につながることがあります。
お教室を替えてみる
習い事そのものをやめる前に、お教室を替えるというのもひとつの方法です。
仲良しのお友達と一緒に通ったり、成果よりも楽しさを優先するようなお教室に移ると、また楽しく通えるようになるかもしれません。
親も一緒にやってみる(低学年までの場合)
低学年くらいまでは、「今日習ったことをママにも教えて」と言って、おうちで「先生役」をやってもらうのも効果的です。
「こんな難しいことやってるの?すごいね!」などと声をかけてあげると、「もっと上手になったところをママに見せたい!」とやる気になってくれます。
何が嫌なのか整理させる(中学年以上の場合)
小学校3~4年生にもなれば、親がおだててやる気にさせることが難しくなります。
その場合は、習い事で「嫌なこと」と「好きなこと」をそれぞれ紙に書き出し、自分の頭の中を整理するように促してみましょう。(※書き出したものを親に見せる必要はありません。)
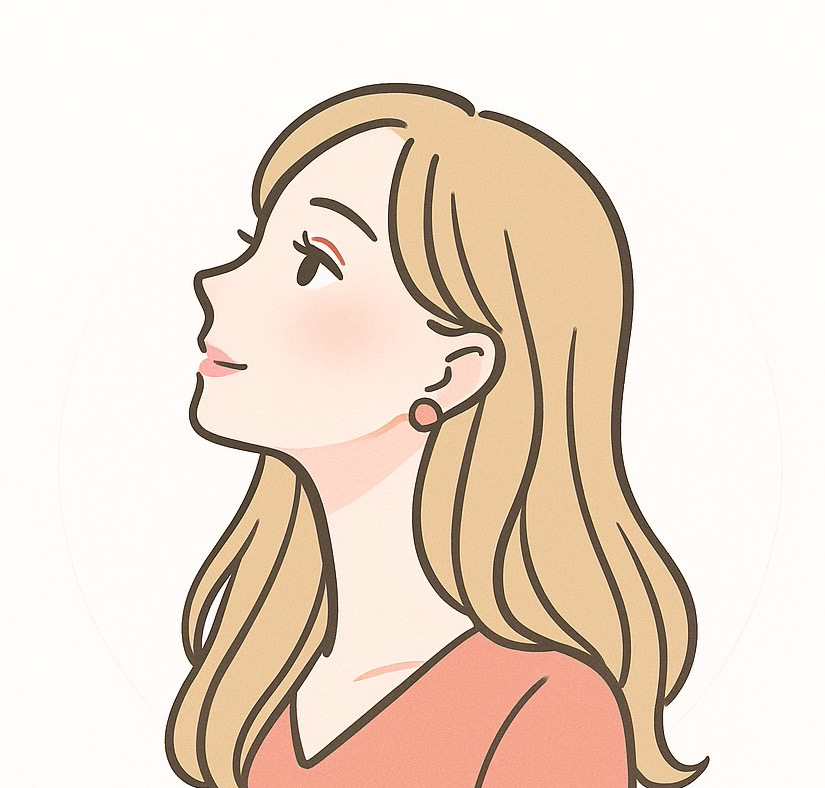
客観的に自分の頭の中を見ることで、「習い事そのものをやめる」「工夫してもう少し続けてみる」「お教室を替える」など、自分で判断しやすくなります。
習い事を見直す
どうしても興味を持てない場合は、別の習い事を検討するのもいいでしょう。本人が「やりたい」と感じる活動に出会えることで、自発的なやる気が戻ることもあります。
やめるタイミングと判断基準
一時的なものかどうかを見極める
学年の変化や友達関係、発表会後の燃え尽き症候群など、一時的にやる気をなくすことはめずらしくありません。数週間〜数か月で改善するようなら、少し様子を見ても良いでしょう。
半年以上続けても改善が見られない場合
半年以上通っているのに「楽しい」という気持ちが見られない場合は、おそらくその習い事が合っていないのでしょう。
「楽しそうだと思ってやってみたけど、自分には合わなかった」ということは大人でもあることです。「自分からやりたいって言ったのに!」などと責めたりせず、「じゃあ、ほかの習い事やってみる?」と前向きな提案をしてあげてください。
子どもが強く「やめたい」と言っている場合
本気で嫌がっているのに無理に続けさせると、習い事だけでなく学ぶこと自体への嫌悪感につながることがあります。子どもの意思を尊重することも大切です。
親が後悔しないための心構え
習い事はあくまで手段である
習い事は子どもの成長を支える大切な機会ですが、あくまで人生の一部にすぎません。やめても子どもの可能性が閉ざされることはありません。
「やめる」選択も前向きに
やめることは決して失敗ではなく、新しい挑戦へのきっかけになります。合わなかったと気づけることも立派な学びの一つです。
親子で納得して決める
親が一方的に決めるのではなく、子どもと一緒に話し合い、納得して結論を出すことが重要です。お互いが前向きな気持ちで判断できれば、後悔も少なくなります。
やめる=挫折と思わせない
「やめる=挫折」ではありません。やめることは新しい可能性を広げる選択でもあるのだと伝えることが大切です。
うちの子にはこれが効いた!親子の工夫実例(低学年までの場合)
実際に小学校低学年のお子さんを持つ親御さんが試して、効果を感じた「やる気アップの工夫」をご紹介します。
スタンプカード作戦
習い事に行くたびにシールを貼り、10個たまったら「親子でおやつ作り」。小さな達成感が続くきっかけになったようです。
ごっこ遊びで楽しく復習
家で「先生役」と「生徒役」を交代しながら遊ぶと、学んだことを楽しみながら復習でき、習い事のある日を楽しみにしてくれるようになりました。
親も一緒にやってみる
親がやったことのないものであっても、一緒にやってみることで「一人じゃない」と安心したようで、前向きにがんばれるようになりました。
小さな変化を具体的に褒める
「いつもつっかかるところがスムーズにできたね」など、小さな変化を褒めるようにしていたら、子どもが自分から練習をするようになりました。
特別なお楽しみをつくる
習い事のある日は、帰りにファストフードに寄ったり、アイスやクレープを一緒に食べるなどして、「習い事=楽しい思い出」になるようにしました。
習い事のお迎えには下の子を実母に預けるなどして、「ママとふたりきりの時間」にしたのもよかったと思います。
親が口出しせずに見守るための考え方(中学年以上の場合)
次に、中学年以上のお子さんを持つ親御さんが取り入れた、「親が口出しせずに見守るための考え方」を紹介します。
進路を決める予行練習だと考えた
もっと成長すれば、進学や就職など、自分で自分のことを決めなければいけません。その予行練習だと思って黙って見守りました。
あえてべつのことを勧めてみた
あまのじゃくなところがある子なので、あえてべつの習い事を明るく勧めてみました。そうしたら効果は抜群で(笑)、もともとやっていた習い事にやる気が出てきたようでした。
才能は遺伝すると感じるように仕向けた
夫婦ともに同じ競技の選手でした。娘も幼少期から当たり前のようにその競技を始め、ひいき目に見ても「才能がある」と感じます。
娘が「やめたい」と言ってきたときは反対せず、「ちょっと休んでみたら?」と提案しました。
そして休んでいる間に親子の似ている部分をさりげなく話題に出すようにしていたら、「遺伝って不思議だね…」と言って、気がつくとまた競技に向き合うようになりました。
まとめ 習い事は楽しむもの
子どもが習い事に対してやる気をなくすのは、めずらしいことではありません。
子どもが強く「やめたい」と訴える場合は、無理に続けさせるのではなく、やめることを前向きに考えてみましょう。やめて時間ができれば、子どもが本当に打ち込めるものに出会えるチャンスも広がります。
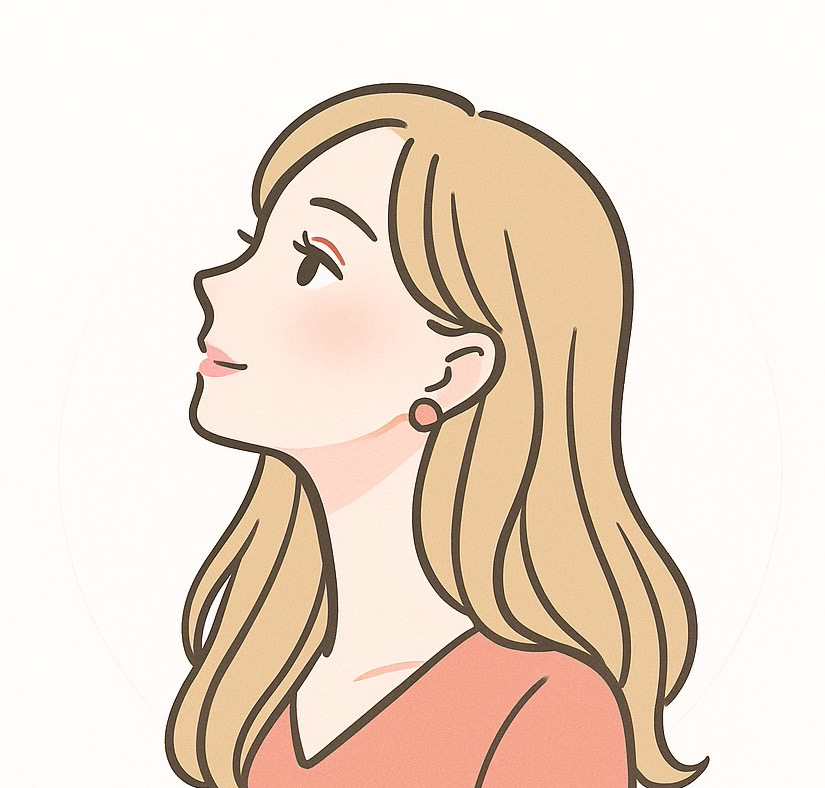
本来、習い事は楽しむものです。将来、「あの習い事、楽しかったな」「習わせてくれたお父さんお母さんありがとう」と思ってもらえるような、いい思い出にしてあげたいですね。



コメント